「この設計料って、どう決まったの?」 そんな疑問を抱いたことはありませんか?
建築プロジェクトのコストは、
- 設計監理契約(アイデアと図面+監理のサービス)
- 工事請負契約(モノを完成させる責任)
という 2本柱 で決まります。
本記事では、
- 設計監理料の 3つの算出方式
- 施工費を形づくる 原価ピラミッド
- 公共と民間で異なる利益の作り方
を最新基準(令和6年告示8号、2025年方針)とともに一気に整理。
数字で語れるエンジニアになるヒントを、5分で掴んでください。
契約形態は2本柱

建築に関する契約は大きく「設計監理契約」と「工事請負契約」の2つがあります。
それぞれの契約の特徴概要が下表です。
| 契約 | 役割・概要 | 典型的な根拠法令 | よく使われる契約書式 |
|---|---|---|---|
| 設計監理契約 | 図面の作成(設計)と、工事が図面通りに行われているか確認(監理)をワンパッケージで請け負う。 | ・建築士法(第25条〈設計・工事監理契約〉) ・民法(準委任契約) | – 民間(七会)連合協定工事請負契約・設計監理業務委託契約約款 – JIA(日本建築家協会)B201シリーズ |
| 工事請負契約 | 建物を「完成」させて引き渡す義務を負う。 目的物が完成して初めて報酬請求権が発生。 | ・民法(請負契約)第632条〜 ・建設業法(第19条〈請負契約の締結及び履行〉) | – 公共工事標準請負契約書(国交省営繕・土木直轄) – 民間(七会)連合協定工事請負契約約款(甲・乙) |
ポイント
- 設計監理契約は「準委任」色が強く、成果物よりも“業務そのもの”に対する対価。
- 工事請負契約は「目的物の完成」が主眼で、出来形に瑕疵があれば責任期間内に無償補修。
また、近年はデザインビルド(設計施工一括方式)が増えています。
技術革新などにより独自工法を交えた設計とした方がコストメリットが高いことが要因です。
この傾向は、より進むことが予想され、設計事務所は基本設計業務や監修業務が増加していくことが予想されます。
設計監理料の算出方法 ──3通りの算出ロジック
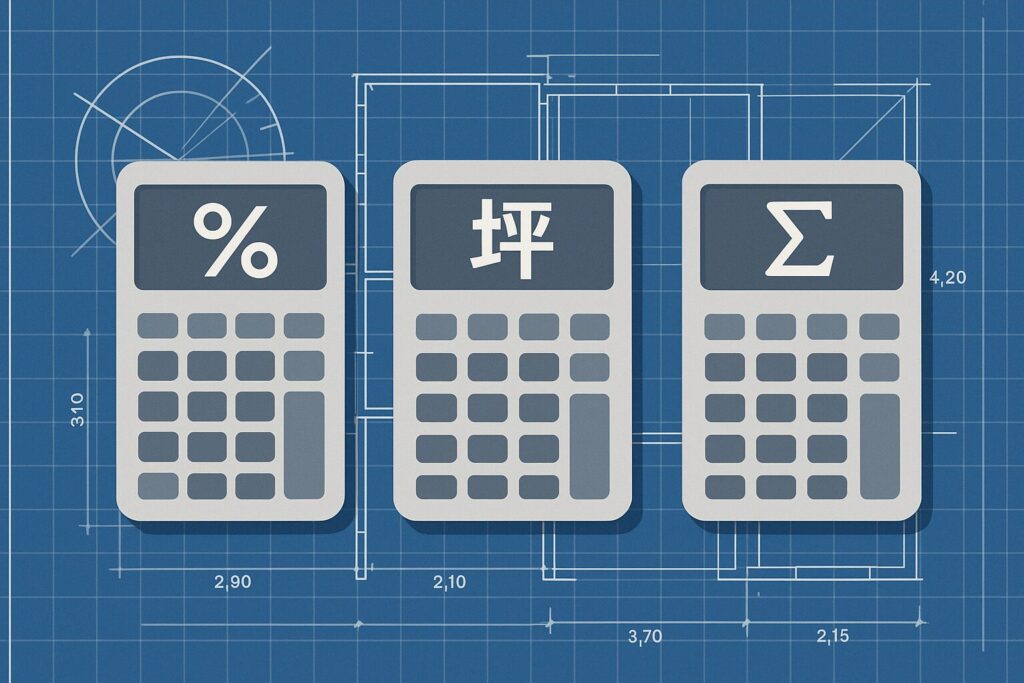
設計監理料の算出方法は大きく「工事費割合方式」「坪単価方式」「国交省標準積算式」3つの方法が一般的に用いられています。
基本的に、設計業務の業務報酬は、建築士法第25条に計算方法などが示されています。(国交省標準積算式)
契約金額はこの方法に準拠したものとするように「努めなければならない」とされています。
つまり、努力義務として定義されており、他2つの方法も違法ではないですし、小規模な設計事務所などでは未だに用いられる方法です。
工事費割合方式
文字通り工事費に対する割合で、設計監理料を算出する方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| しくみ | 設計監理料 = 総工事費 × 料率 |
| 相場感 | 本体工事費に対し 10〜15 % が目安 |
| 特徴 | “ざっくり予算”を把握しやすい 規模が大きくなると料率が低減(スケールメリット) |
| 備考 | 追加・変更工事で工事費が膨らむと、設計監理料も自動的に増額。 |
比較的小規模PJを扱う設計事務所や住宅メーカーで用いられていることがあります。
お客さんとしては、価格が把握しやすいことがメリットでしょう。
設計行為は、ある程度やることが決まっているので、規模が大きくなった分だけ業務量が増えるわけではありません。
そのため、規模が大きくなるについて、スケールメリットが働くことになります。
逆に、小規模案件の場合には、設計者目線からは割の合わない仕事になってしまいがち。
坪単価方式(1坪 8 〜 18 万円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| しくみ | 設計監理料 = 延べ床面積(坪) × 坪単価 |
| 相場感 | 1坪あたり 8〜18 万円 |
| 特徴 | 初期段階で面積が決まっていれば試算がカンタン 工事費の増減に左右されないため“面積の正確さ”がカギ |
| 備考 | 最低料金を設定されている。(小規模での赤字回避) |
この方式も比較的小規模PJを扱う設計事務所や住宅メーカーで用いられていることがあります。
相場感だけ抑えておくと、大規模案件での設計業務査定などにも活用できます。
国交省標準積算式 ★公共案件&大規模民間で必須
建築士法25条に基づき、国土交通省が告示として具体的な方法を示したものです。
それについて、国土交通省は令和6年告示第8号で「業務報酬基準」を全面改定し、算出式と略算表を公開しています。国土交通省
報酬(設計監理料) = 直接人件費 + 諸経費 + 技術料 + 特別経費 + 消費税
| 要素 | 現場で決めるポイント |
|---|---|
| 直接人件費 | 技師ランク別日額×工数。 例:技師C=38,400円/日(R6単価)国土交通省 |
| 諸経費 | 事務所賃料・光熱通信費など。直接人件費の100 %前後が多い |
| 技術料 | 知識・経験への対価。直接人件費の*50 %*程度を標準に、設計難度で補正 |
| 特別経費 | 遠隔地出張や特許使用料などプロジェクト固有の費用 |
| 消費税 | 報酬合計に10 % |
メリット
- 発注者(官庁)が予定価格を算出する根拠式と完全リンク
- 年1回改訂される単価表に追随すれば価格協議が通りやすい
デメリット
- 工数把握が甘いと “後で赤字” に陥る
- 技術料に上限目安があるため、独自ブランド料を乗せづらい
まとめ:式を使い分ければ“説得力”が変わる
- 工事費割合方式 … 施主がコスト感をつかみやすい。
- 坪単価方式 … 面積が決まったら即試算、リノベ向き。
- 国交省標準積算式 … 公共・大規模で必須、単価改定を追う!
覚えておくべきは “根拠を示せるか”。
どの方式でも、計算プロセスを開示すれば価格交渉は驚くほどスムーズになります。次の案件から、見積書に「算出方式:〇〇方式」「工数根拠:別紙○○」と明記してみましょう。数字で語れる設計者は、現場でも必ず信頼されます。
工事請負契約 ──原価ピラミッドと利益率

【請負金額】
└──一般管理費等(本社経費+利益)
└──現場管理費(現場事務所運営)
└──直接工事費
├ 材料費
├ 労務費
├ 外注費
└ 直接経費(仮設・重機 等)
| 階層 | 構成 | 主な中身 |
|---|---|---|
| ① 一般管理費等 | 本社経費+利益 | 経営陣・管理部門人件費、研究開発費、広告費など |
| ② 現場管理費 | 現場事務所運営費 | 監督員人件費、安全・品質・環境管理費、福利厚生費 |
| ③ 共通仮設費 | 共通仮設物 | 仮囲い、ゲート、仮設電気・上下水、足場など |
| ④ 直接工事費 | 純粋原価 | 材料費、労務費、機械経費、専門工事外注費 |
公共工事
- 公共建築積算基準により、ルール化
- 共通仮設・現場管理費は国の指数式で自動的に決まる(公共建築工事共通費積算基準)
- 物価スライド・年1回以上の価格協議が義務化(2025年 方針)
民間工事
- **積算原価+本社経費5〜8 %+利益5〜10 %**が目安
- コスト制約時は 原価+フィー契約 や GMP を活用
- リスクプレミアムで利益率が10 %超になるケースも
公共 vs. 民間 算定ルール早見表

| 観点 | 公共工事 | 民間プロジェクト |
|---|---|---|
| 資金 | 税金 | 施主自己資金・融資 |
| 発注方法 | 原則入札 | 随意・ECI・GMPなど自由 |
| 単価根拠 | 国の積算基準・単価資料 | 市場実勢+社内標準 |
| 利益率 | 設計≈30 %上限・施工6 %標準 国土交通省 | 交渉次第で変動(5〜15 %) 本社経費5〜8 %+利益5〜10 %が目安 アーキブック |
| 価格変動 | 物価スライド・年1回協議必須 | 契約条項で個別合意 |
| 手続き | 書類多い・透明性重視 | 迅速だが責任範囲を要確認 |
公共発注と民間発注は、同じ建設プロジェクトでも 資金の性格・法的規制・収益の作り方 が根本的に異なります。下表で俯瞰したあと、各項目をプロ目線で補足します。
資金と発注方式
公共は“税金”ゆえ 透明性・公平性 が最優先。
予定価格作成→入札公告→落札決定という一連の手続に会計法・予算決算令が紐づきます。
一方、民間は施主の調達戦略次第。早期に施工者を巻き込む手法でコストとスケジュールを握るケースが増加中です。
単価と利益の“ブレーキ&アクセル”
- 公共: 労務単価・資材単価・共通費率を国交省基準で確定。その上で施工者利益は 標準6 %。高リスク高難度でも大幅上積みはできません。国土交通省
- 民間: 単価は相見積+社内データ。利益は 5〜10 % を目安に、リスクプレミアム(鋼材高騰、長納期設備など)を載せていくのが一般的です。アーキブック
価格変動への“守り”
公共は 第26条(インフレスライド)協議 が制度化され、「賃金・資材価格が変動すれば年1回以上協議」が発注者義務。2025年からは中小企業配慮で協議請求“待ち”を禁止しました。国土交通省
民間は契約に「上限±○%まで吸収」「リスク共有プールを設定」など自由設計。ただし買い手優位の場合はリスクを請負者が背負わされるケースも。
書類・検査・IT化
公共は電子調達システム(電子入札・電子納品)が必須。
完成検査・出来高検査で書類不備があると支払遅延につながります。
民間は電子署名の採否も自由ですが、最近はBIMモデル引渡しやクラウド監理プラットフォーム導入が加速中。
まとめ
公共=“規範”で積む、民間=“交渉”で積む。
ルールの違いを理解すれば、見積・契約・価格協議の“打ち手”が変わります。
次の案件ではぜひ 「この条項は公共なら○○、民間なら△△」 と言語化し、原価と利益を“意図して”設計してみてください。数字で語れるエンジニアは、プロジェクトの舵を握れます。
若手が押さえるべき“4つの実務 Tips”
- 最新単価をウォッチ
- 国交省PDFは春に改訂。
- 原価内訳書を即説明できる形で保存
- 価格協議の肝は“根拠の見える化”。
- BIM・i‑Construction 2.0の提案力を磨く
- 技術提案点が高いと価格以外で勝負できる。
- 利益率=悪ではない
- 適正利潤を確保してこそ品質と安全が守れる。
- “薄利多売”は倒産リスクを高めるだけ。

まとめ
契約は2本柱
- 設計監理契約 は「準委任」=業務そのものへの対価。
- 工事請負契約 は「請負」=完成物への対価・瑕疵責任付き。
設計監理料は3方式で算定
- 工事費割合方式 ― 10〜15%が目安、予算把握がラク。
- 坪単価方式 ― 1坪8〜18万円、小規模住宅で使いやすい。
- 国交省標準積算式 ― 公共&大規模で必須。
→ 「どの方式か」を明示し、工数根拠を添えると交渉に強い。
施工側は“原価ピラミッド”で積む
- 直接工事費 → 共通仮設費 → 現場管理費 → 一般管理費等(利益含む)。
- 公共は指数式・利益6%標準、民間は交渉で5〜15%がレンジ。
公共 vs. 民間=規範と交渉のコントラスト
- 公共:税金ゆえ透明性最優先、物価スライド&年1回協議が義務。
- 民間:資金も条項も自由度高く、リスクプレミアムで利益を守る。
若手が今すぐやるべき4つ
- 最新単価を毎年アップデート。
- 原価内訳書を“説明できるフォーマット”で保存。
- BIM/i-Construction 2.0で技術点を稼ぎ、価格競争を緩和。
- 「適正利潤=品質・安全の担保」という視点で堂々と利益を主張。

おすすめ参考書
「Kr・Gp の計算例、もう探さなくてOK——公式解説書の決定版」
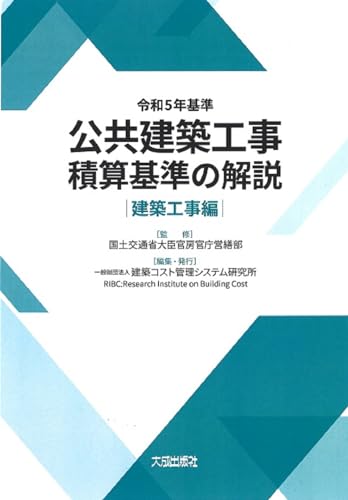
令和5年基準 公共建築工事積算基準の解説(建築工事編)
「最新トレンド×図解だから、移動中にサクッと業界アップデート」
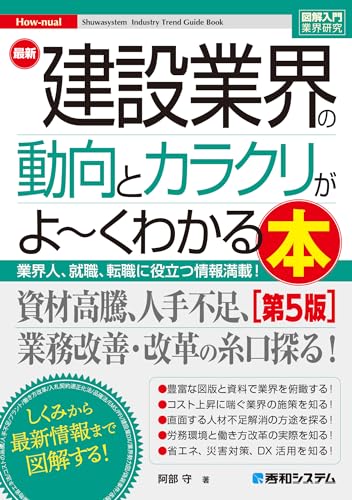
図解入門業界研究 最新建設業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[第5版]
「条文が苦手でも30分でわかる!マンガで約款デビュー」
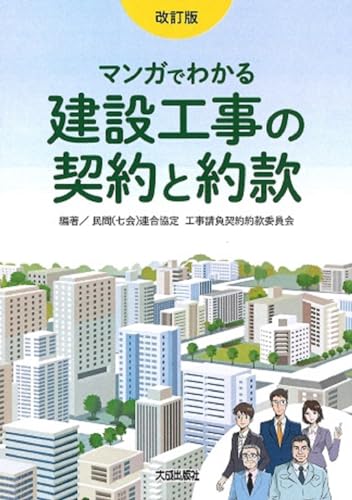
改訂版 マンガでわかる建設工事の契約と約款
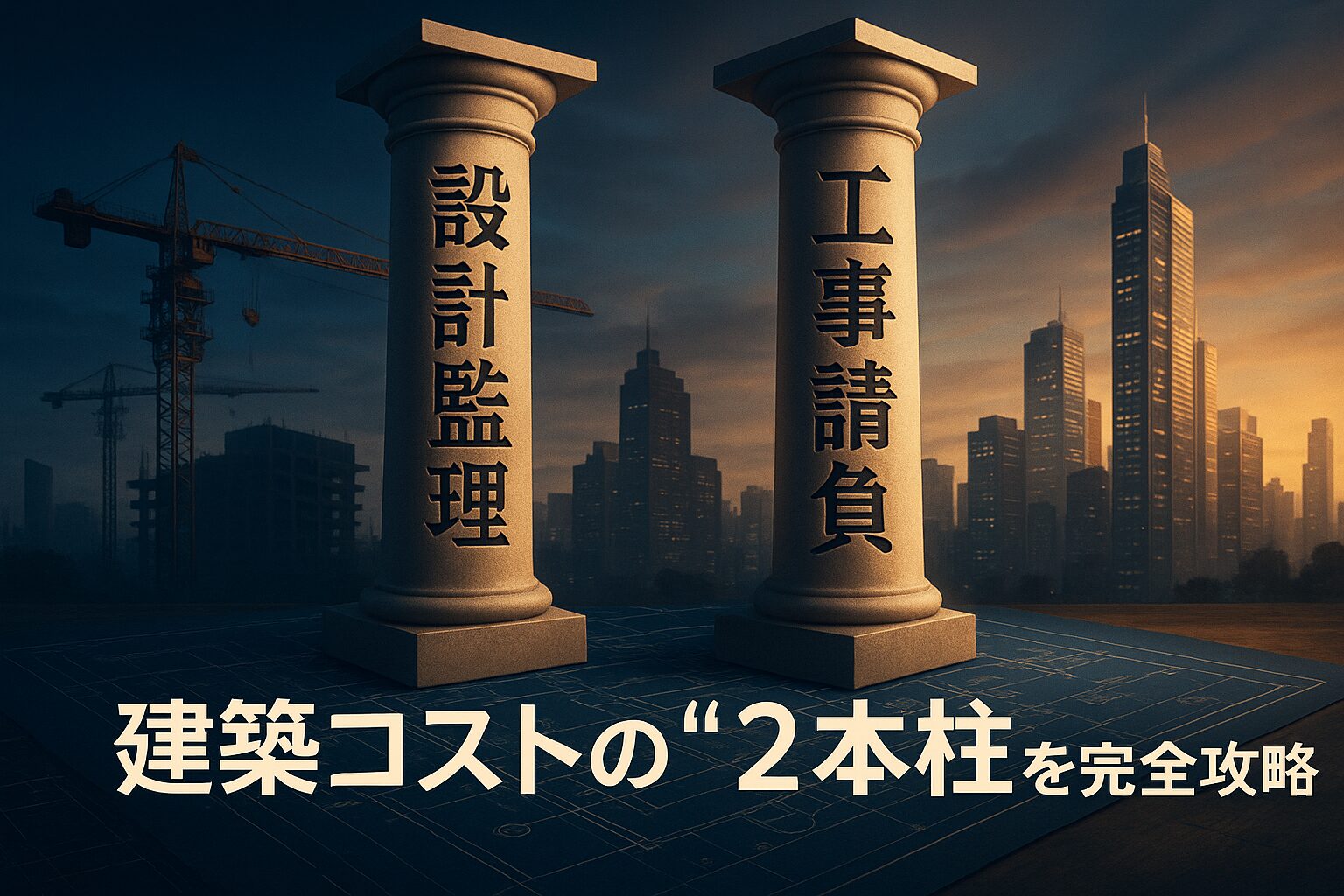
コメント