はじめに – この記事で学べること
建築士がクライアントに設計内容を説明するとき、図面やデザインを見せるだけでは不十分です。
相手の不安やリスクを理解し、それをどうヘッジしているかをわかりやすく伝えることが、プロジェクトの成功を左右します。
この記事では、
- クライアントが抱えるリスクとその背景
- 優れた建築士が実践する説明・プレゼンのポイント
- 人気書籍や他業種から学べるプレゼン術
- 実務に使えるヒアリングや資料作成の工夫
を具体的に紹介します。
読み終えるころには、クライアントの信頼を得ながらプロジェクトをスムーズに進めるための「伝える力」が身につくはずです。
実体験から学んだ「伝える力」とリスク説明の重要性

私はこれまで、設計者としてもクライアントとしてもプロジェクトに関わってきました。
その中で強く感じたのが、「クライアントのリスクを理解して伝えること」の大切さです。
クライアントは、意識していなくても不動産投資をしている立場にあります。
土地や建物は大きな資産であり、その取得・建設には多額の費用がかかり、必ずリスクが伴います。
優れた建築士は、そのリスクを先回りして説明し、「完全にはなくせないが、こうやって最大限ヘッジしています」と具体的に伝えます。
また、クライアントが企業として建物を建てる場合、担当者は社内の意思決定を進める役割を担っています。
建築士は「社内承認が得やすい提案」「リスク説明資料として使える情報」など、次のステップに進める材料をヒアリングし、提示する必要があります。
実際、私が設計者としてリスクと対策を丁寧に説明した案件では、工事中の変更やトラブルが最小限に抑えられました。
逆に、クライアントとして説明不足な案件に関わったときは、後から予算やスケジュールが大きく変わり、不満を抱くことになりました。
どれだけ技術や経験があっても、リスク共有ができなければ、クライアントは「本当に大丈夫か」と不安を抱いたまま進めることになります。
だからこそ、背景や立場を理解し、リスクも含めた全体像を明確に伝える力が不可欠なのです。

クライアントの思考と不安を読み解く
建築士はつい専門知識を基準に考えがちですが、クライアントが抱く期待や不安を知ることが大切です。
経験と資料をもとに整理すると、次のような傾向があります。
| 観点 | 主な思考・悩み |
|---|---|
| 目的 | 理想の住まいをどう形にすればいいか分からない |
| 知識の不足 | 法規や条件、予算に合う選択肢が分からない |
| 不安とリスク | 高額投資だから失敗したくない |
| 価値観の多様性 | 好みや暮らし方をうまく言葉にできない |
| 信頼関係 | 自分の意図を理解し、真摯に対応してくれるか見極めたい |
つまりクライアントは、「希望を形にしてくれる」という期待と、「素人だから判断できない」という不安の間で揺れています。
そのギャップを埋めるのが建築士の説明力です。

人気書籍から学ぶ建築プレゼン術

『建築プレゼンの掟』(彰国社)から得られる5つのポイント
建築プレゼンにおける基本姿勢をまとめた書籍『建築プレゼンの掟』では、次のようなルールを掲げています。
- 一つの画像に一つのメッセージ – 情報を詰め込みすぎない
- 物に語らせる – 模型やサンプルで質感やスケール感を伝える
- 感覚に訴える – 実物大のサンプルで空間の雰囲気を体感してもらう
- 価値基準に寄り添う – 相手が納得できる判断軸を示す
- 潔く削る – 情報過多を避ける

建築プレゼンの掟 (建築文化シナジー)
『建築家が教える人生を変える驚異のプレゼン』(エクスナレッジ)から学べるポイント
この書籍では、著名建築家のプレゼン技術が紹介されており、下記のようなポイントが挙げられています。
- プロセスの提示:完成形だけでなく、敷地分析や要件整理といったプロセスも見せることで、設計の必然性を示し、クライアントを参加者にする。
- 物語性の重視:単なる説明ではなく、コンセプトに基づいたストーリーをつくり、施主が感情移入できるようにする。
- 会場や聴衆に合わせた表現方法の使い分け:コンペや個別住宅など、相手の属性に応じて主眼を変える

建築家が教える人生を変える驚異のプレゼン (エクスナレッジムック)
建築士が実践すべき説明・プレゼンのポイント
. 徹底したヒアリングと共感
- クライアントの「本当にやりたいこと」を丁寧に聞き出す
- 専門用語を避け、理解度に合わせた説明をする
- 上下関係ではなく、対等なパートナーとして接する
2. 視覚資料と五感に訴えるツールの活用
- CGパースや3Dモデルで立体的にイメージを共有
- 模型や実物サンプルで質感・スケール感を伝える
- 手描きスケッチで温かみや情熱を表現する
- プレゼンボードは不要な情報を削ぎ落とし、視線の流れを意識する
3. 構成とストーリーづくり
- PREP法やSDS法で分かりやすい流れにする
- エピソードを交えて感情にも訴える
- 詳細データは別資料にして、本編は要点に集中
4. 根拠と透明性の確保
- 初期段階で予算・スケジュール・制約条件を共有
- 法規や敷地条件も図や事例で説明し、納得感を高める
5. フィードバックと修正
- 段階的に確認を取りながら進める
- 質問しやすい雰囲気をつくり、不明点を残さない
クライアントと設計者が共に成長するために
クライアントが求めているのは、図面だけではなく、自分たちの価値観や目的を理解した上での最良の提案です。
建築士は技術者であると同時に、クライアントの代弁者であり、リスクを正しく共有するパートナーです。
ヒアリング・視覚化・ストーリー・根拠説明を組み合わせたプレゼン力で、不安を安心に変え、プロジェクトを成功へ導きましょう。
建築プレゼンは一方通行ではなく、施主と共につくる「共同作業」なのです。
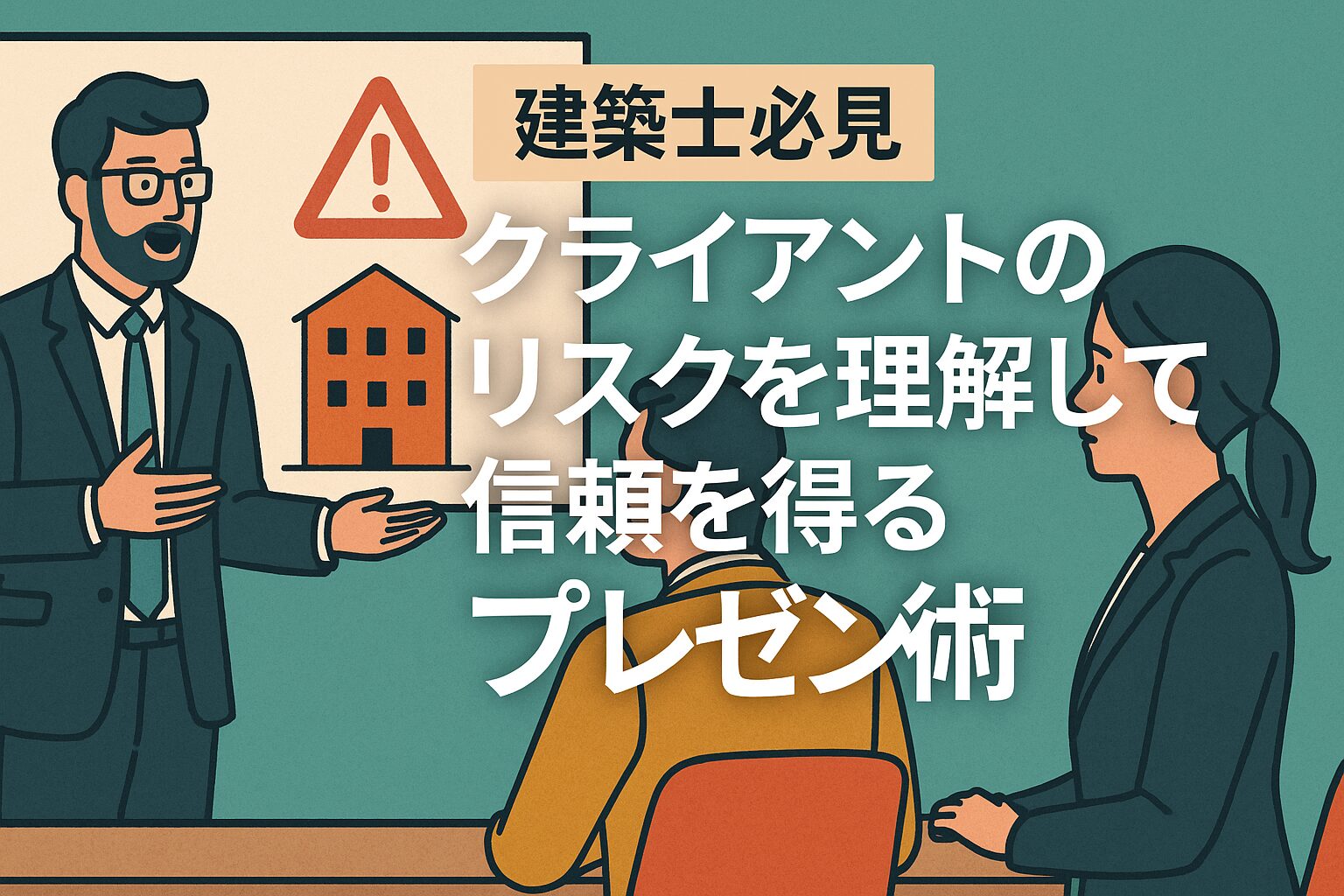
コメント